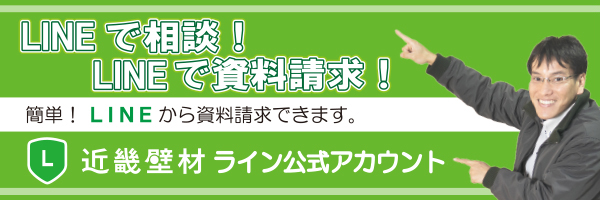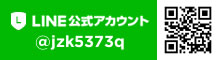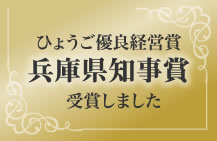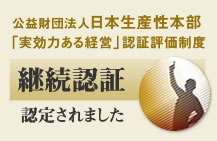寒い時期発生する現象「白華」とは? |
・
ウルトラソイル施工したけど・・・白くなっちゃった?なぜ?
・
寒い時期の土間たたき施工は、乾燥後白いムラが出来ます。
≫ウルトラソイル施工の様子撮影してきましたブログはこちら・・・
・
白華とは何か?
白華(はっか)は、諸説ありますが、以前「白華」について書いた文章があったので転記します。
左官材料(モルタル・漆喰・土間等)における白華(エフロレッセンス)の問題
現在、左官工事関する白華、色ムラの問題は、解決することの出来ない難しい課題となっております。
しかし、原因と考えられる点を克服すれば、ある程度の改善できると考えられます。
① 白華の原因
白華は、石灰及びセメント系左官材料に必ずある問題です。
当社でも長年、防御策及び補修方法は確立されておりません。
色付きの材料、冬場の施工、雨の掛かる場所への施工、などに多く見られ、色むらの原因も白華現象の一種と考えております。
白華は、練り水や雨水などによる遊離石灰が原因といわれております。特にセメントや石灰系材料は、水酸化カルシウムが乾燥し炭酸化され炭酸カルシウムになります。この炭酸カルシウムの結晶が、水に溶けず白くなり表面にのこり白華になります。
その中でも、白華は大別して2種類あると考えられており、材料内の練り水で起る1次、施工後の雨水などで起る2次があります。
◇1次の白華について
1次の白華は、材料の練り水との反応により起る現象です。練り水の量が多いと溶け込むアルカリ分の量も多くなることから乾燥と同時に表面に発生する白華の量も多くなります。
- 施工上の原因によるもの
左官材料を施工の場合、最終の押さえ工程があります。その中で押える回数や、力などにより表面の水分量にバラツキが出ることで白華します。特に押さえが少ないところは、水分が多く残ることから色が薄くなります。
- 下地の水引きが原因によるもの
鏝押え同様に下地の水引を一定にしなければ、特に水持ちが良い部分は白華しやすくなります。仕上げ面において新聞紙などで水分を吸い取るのもこの為です。
- 材料の配合が原因によるもの
材料の配合を同じにしても、水の量が違う場合色は変わり、特に軟練りの場合は、白華がしやすくなります。
水の量が多いと当然浮き水の量は多くなり、白華の原因となるアルカリ分が乾燥と同時に多く上がってきます。
- 季節的な原因によるもの
白華は特に冬場に起ります。アルカリ分(水酸化カルシウム)の量は、低温になるほど多く現れ、乾燥速度が遅いほど結晶の大きさは大きくなります。しかも、蒸発は表面よりすべて蒸発することから表面に結晶が現れ白く見えます。白華の原因の多くは、この蒸発速度にあり冬場のように気温が低く、湿度が高い場合は、特に危険です。
◇2次白華について
2次白華の原因は、施工後の雨などによる水掛かりによるものがほとんどで、石灰系材料は、空気中の炭酸ガスを吸いながら硬化し、炭酸カルシウムに変化してゆくのに長期間有します。よって表面が乾燥していても水分により再度溶解し、アルカリ飽和溶液となって乾燥と同時に壁表面に白く結晶を浮き上がらせます。
磨きなどで手擦りを行った後でも1週間空拭きを行い、毎週・毎月・毎年と手入れをしなくてはならないのはそのためです。
以上の事から、白華原因は特定できませんが、塗厚による水分量の違いによる斑による白華、冬場施工による気温の低下に伴う蒸発速度に伴う白華、施工後の養生不足での雨掛りによるアルカリ分の再溶解による表面の結晶化と考えられます。このことより、表面のみの白華現象と予測ができますので、対応策として次に考えて参ります。
少し話が脱線しましたが、もともと白い材料なら目立ちませんが、ウルトラソイルは色が付いているためそうはいきません。
そこで当社では、土間たたき製品カタログや施工方法にも明記してあるように、施工後乾燥してから白華を除去する酸洗いをおすすめしております。
酸洗いには専用品「たたき洗浄剤」をご利用ください。

≫たたき洗浄剤の購入はこちら・・・
白華でお悩みの方はお問わせください!