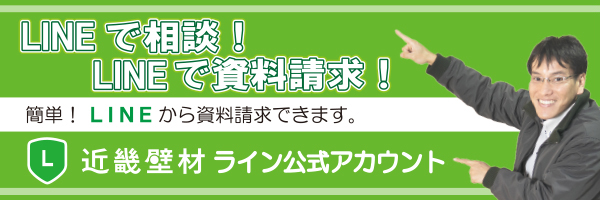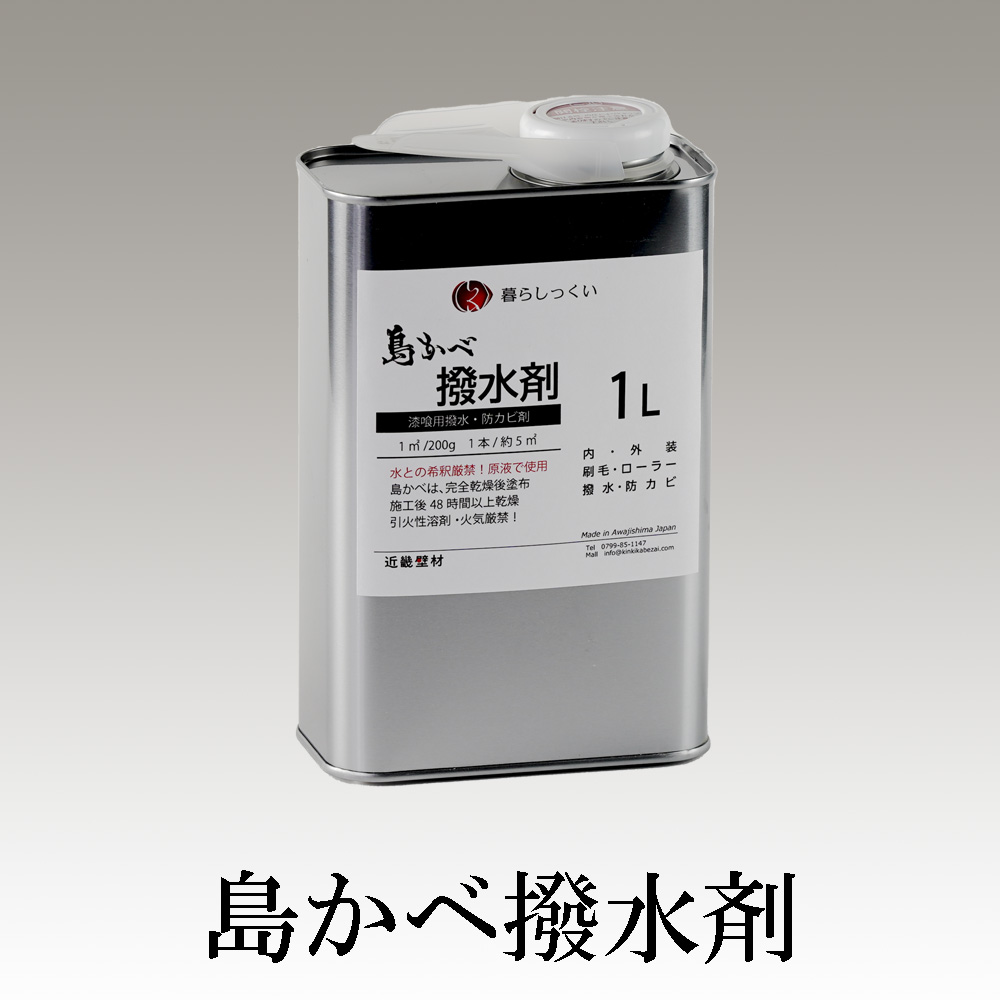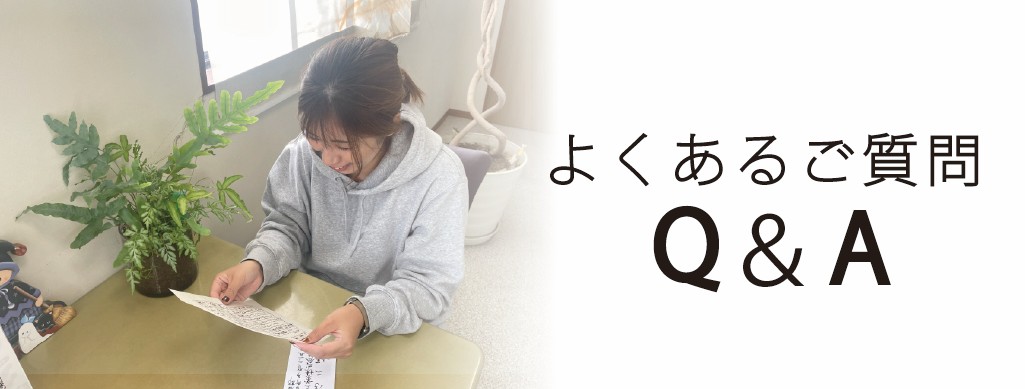性質上漆喰の方がカビが生えにくい、ただし条件が揃えば漆喰にも発生する
先日古民家を購入し、改修をDIYでする予定のお客様からお問わせをいただきました。
購入した古民家は数年間空き家になっていたそうで、壁には土壁が施工されているそうです。
購入のポイントは立地や家の状態の良さもあったそうなのですが、土壁に囲まれた部屋の風合いの良さも気に入ったポイントでした。
ただ、数年間空き家で締め切った状態だったので、土壁にはカビが生えているそうです。お客様は土壁の風合いをとても気に入っているので、再度新しい土壁を施工して改修したい気持ちがあるのすが、カビが発生している現在の土壁を見て、土壁を選択すると再びカビが生えるのでは?と気になされていました。

そこでお客様は自分でお調べになり、漆喰がカビに強い、生えにくいという事を知り、漆喰を施工するべきなのか、それとも気に入っている土壁を選択するべきなのか悩んでおり、ご相談をいただきました。
お客様がお調べになったとおり、「漆喰」と「土壁」を比較した場合、カビが生えにくいのは「漆喰」です。ただし、たとえ「漆喰」を選択してもカビの発生条件が揃えば、漆喰にもカビは発生します。

現在の土壁にカビが生えている原因として、数年間空き家で締め切り状態で空気の流れなどがほとんどなかったことも大きいと思います。これからはお客様がお住まいになるので、日常的に窓やドアの開閉、人の動きもあり、空気の流れができます。それだけで今までとは屋内環境は全く違うものになり、カビがより発生しずらい環境になります。
素材だけで考えると「漆喰」の方がカビが発生しずらいのは確かですが、一番の原因はその環境条件なので、「漆喰」「土壁」どちらを選択したとしても、空気の流れを作ってあげることは重量です。「漆喰」「土壁」どちらも呼吸する壁材で湿気を吸う調湿性能がありますが、吸うばかりではなく、吐き出す環境も作ってあげることが必要ということです。

また、この度のお客様のように現在カビが生えている壁の上に塗り重ねて改修する場合は、現在発生しているカビを除菌や除去することも重要です。そのまま塗り重ねると、もともとカビ生えていた部分から再度カビが新しく塗った壁表面まで出てきます。
漆喰や土壁が持つ調湿性能も万能ではなく、生きている壁なので、吸った湿気を吐き出す環境も作っていただくことを意識していただけるとカビ対策になります。