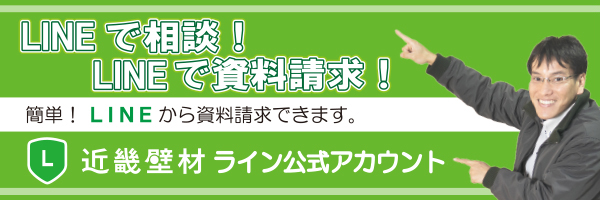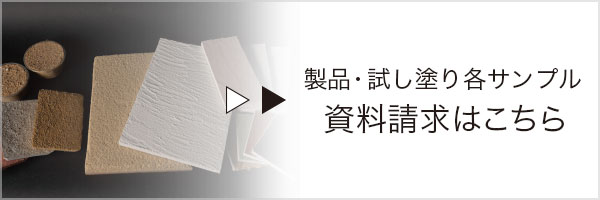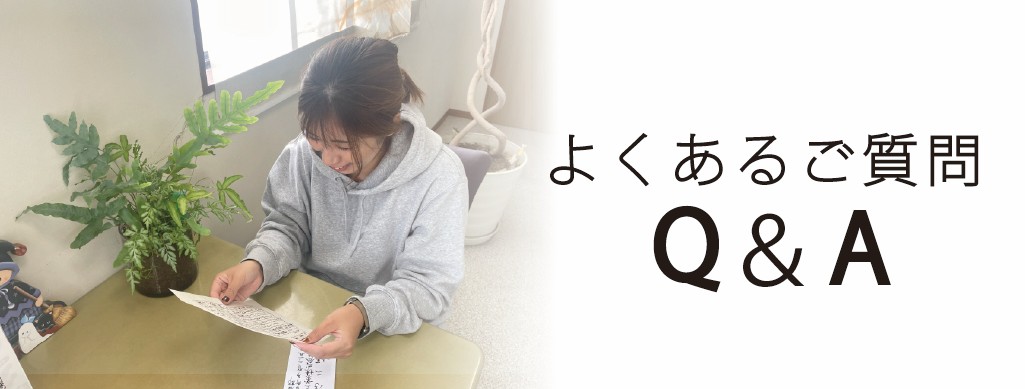砂漆喰(中塗り漆喰)は昔は高価だった?

今では漆喰仕上げの中塗り(不陸調整材)としても必要不可欠の砂漆喰ですが、すべての状況において必ず使われていたわけではないようです。
古い建物の修繕や解体、または一部欠損している場所を確認しても、土中塗りの上に上塗り(通常の漆喰仕上げ)がされているのをよく見ます。
もちろん城郭建築や土蔵など、漆喰による大壁仕上げなどの場合は、十分な厚みで砂漆喰が塗られていますが、社寺や書院造りなどの真壁造の建築では以外に砂漆喰は使われていません。
考えるに・・・(何の根拠もない仮説ですが)
①そもそも昔は石灰が高価で一般の住宅には大量に使用できなかった?
②土壁の精度も高く不陸調整の必要が無かった?
③建築様式で軒が長く、直接風雨にもさらされないので厚く塗る必要が無かった?
などの理由が考えられますが、土の上に薄く(2mm程度)上塗りを塗って何十年も落ちずに保たれているのはすばらしいですね。
また、漆喰が剥がれ落ちても漆喰部分だけが綺麗に剥がれるので20~30年程度の定期的な塗替えを心掛ければ、土を傷めず何百年も持つんでしょうね。
漆喰が傷んだら土がむ傷む前にすぐにメンテナンスが必要ですね。
最近は、付着力や強度ばかりに目が行きがちですが、土壁・漆喰は自然素材のただの石灰岩ですから定期的なメンテナンスは当然必要になります。
それでも数十年もつのはすごいですよね。
以前上塗りだけきれいに剥がせる仕事が良い仕事。剥がれればまた塗ればいいじゃない。と言っていた左官屋さんもおられました。
何十年、何百年持つ工法も重要ですが、荒壁や、中塗り土が傷む前に定期的に上塗りだけメンテナンスすれば費用も少なくてすみますしね。
先人はやはりよく考えていたんですね。
<<砂漆喰とは・・・島かべ砂漆喰はこちら
先人の方はどんな方法で土下地に漆喰を塗っていたのか?
では、どんな工法でやってたのか、考えるに・・・(再度根拠のない仮説ですが)
①土に水湿しをジャブジャブしていた。(ちょっと現実的じゃないですよね、ムラ引きしそうです。)
②土に追っ掛けしていた。(これは今でもやられている人は多くいますが、土や藁すさによってはアクが出る場合があるので注意が必要です。特に寒い時期)
③引き糊を使用した。(これも現代でのシーラー替わりですから、今でもやられている人が多くいます。)
④上塗りの漆喰の糊が濃い。(③と近いですが・・・)
あと、土が入っていたり、紙すさだったり、貝灰だったり、色々仮説を考えるとおもしろいですね。
砂漆喰が塗られていない場合。


砂漆喰が塗られている場合

漆喰にご興味がありましたらお問合せ下さい!