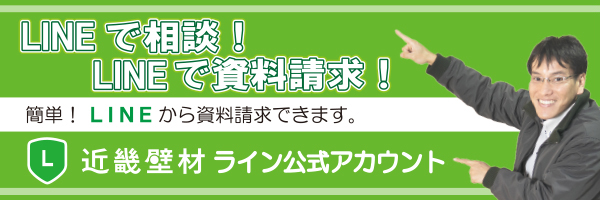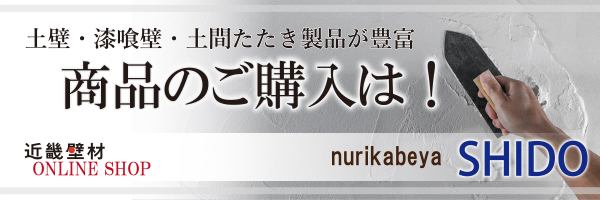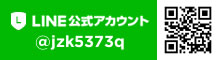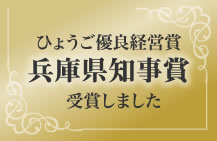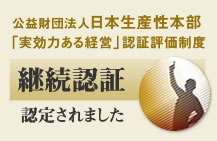土壁は日本で1500年ほどの歴史があり、昔から現在に至るまで、主原料は変わらず「土」「砂」「藁すさ」の3つが使われます。
そんな土壁の材料(素材)をご紹介します!
〇土壁の材料(素材)「土」

はるか昔の時代から私たちの身近にある「土」。
元々、土は日本全国どこでも採取出来ていましたが、近年は建物が建ったり、採取禁止になったりして、塗り壁や土間たたきの素材としての、土の確保が非常に困難になってきました。
しかし、当社がある淡路島は、昔からきめ細かい良質な粘土が採取される産地として有名で、今現在も豊富に採取することができます。
この良質な粘土を元に、栄えた産業が日本三大瓦のひとつ「淡路瓦」で、当社はこのきめ細かい粘土を壁の材料として長年販売させていただいております。
土は粒度により大きく4つに分かれます。
そのなかでも一般的に、土壁は粘土の多い、粘い土が使われます。
土壁などに使用する場合、強度を受け持つのは、ほぼ粘土の部分です。なので粘土が無いと壁材として強度が確保できません。
そういう意味では淡路島の土はきめが細かいため粘土分が多く、壁材にも適した土になります。
<<土壁に使う「土」くわしくはこちら・・・
〇土壁の材料(素材)「藁すさ」

藁すさは、主に土壁の亀裂を防ぐつなぎ材としての役割と、作業性向上効果もあります。
利用場面など使われる土壁により、長さや性質が違うものが使われてきました。
例えば土壁の下地として使われる荒壁の藁すさ「荒すさ」は、厚塗る壁のため、10cm程でカットされた非常に長く太いものになります。
仕上げ(上塗り)工程に近づくにしたがって、土壁に混ぜる藁すさも、より細かく裁断されたものを使用します。
特に最終の仕上げ塗り(上塗り)に混ぜる藁すさは特殊で、「アク抜き」処理を行った藁すさ使用します。
「アク抜き」処理をした藁すさはその名のとおり、仕上げ表面にアクが出にくく、繊維も柔らかいため、うすく塗る仕上げ塗り土壁に適したものになります。
<<土壁の素材、「藁すさ」はこちらから・・・
〇土壁の材料(素材)「砂」
土壁の砂は骨材として混ぜ、乾燥による収縮を軽減し、割れ(クラック)の発生を抑制します。
ただ、砂の配合量を増やせば増やすほど、土壁としての強度が下がるので適量にする必要があります。
「藁すさ」と同じで、仕上げ塗り(上塗り)工程に近づくにしたがって粒度の細かい砂を使用します。
上塗りに近づくほど、塗り厚がどんどんうすくなっていくためです。
<<土壁の素材、「砂」はこちらから・・・
このような土壁の素材の他にも、糊土(のりつち)と呼ばれる仕上げで、海藻糊などを素材として入れる、土壁仕上げもあります。
海藻糊は、土壁の保水性あげたり、作業性を良くします。
土壁は主な3つの材料(素材)に加え、糊や着色材を加えることで様々な使い方、仕上げ、デザインにできます。
◇土壁材料関連ブログは下記から

<<土壁材料について こんな時何を使うの?

<<土壁を塗るための下地材料について

<<仕上げ(上塗り)に使う土壁材料について

<<土壁補修に使う材料について
土壁の素材ならおまかせください!