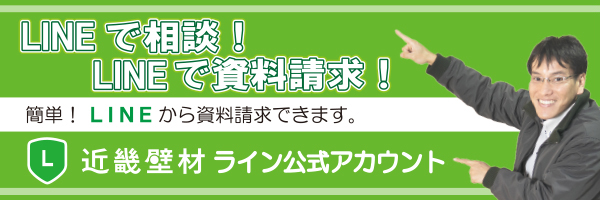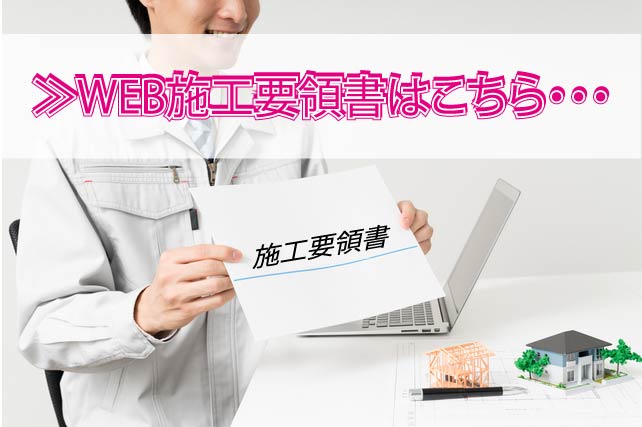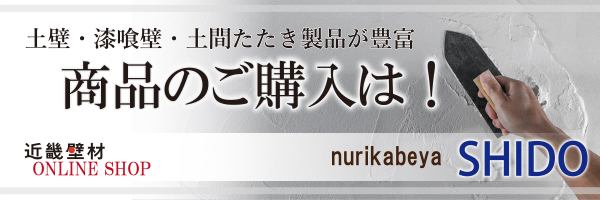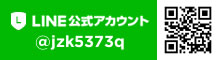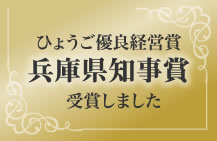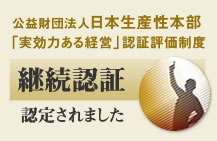ジョイント(継ぎ目)がわかってしまう仕上り
DIYのお客様よりお問わせいただきました。
「新規の石膏ボード(PB)にジョイント処理をして、その後市販のシーラーを壁に塗布し、漆喰を塗ったら、ジョイント部分が目立つ仕上がりになってしまった」
同じお問わせが結構多いので、この度はその理由のと対策をご説明致します。

■ジョイント(継ぎ目)が目立つ理由
・ジョイントのパテ処理作業でフラット(平滑)にできていない
・水でうすめすぎたシーラー材の下地処理性能の低下
・仕上げに塗った漆喰の塗り厚が薄すぎる
特にジョイント処理には「ジョイントテープ(ジョイントネット)」を貼る作業を行うため、テープの厚さ分の凹凸が必ずできます。この凹凸をなくす作業がパテ処理になりますが、ご経験のある方はわかると思いますが、これが結構難しい作業です。
ここで凹凸をなくしておかないと、上に塗る漆喰は2ミリ程度の厚みで塗る材料のため、ジョイントテープの膨らみがわかる仕上りになります。
もし、このパテ作業でかなりフラット(平滑)に下地処理できていたのに、ジョイントが目立つ仕上がりになったのなら、シーラー材を水でうすくしすぎたか、漆喰の塗り厚がうすいかのどちらかです。


ジョイント(継ぎ目)の膨らみを隠せる下地材
では、ジョイントが目立たないようにする対策はどのようにするればよいのかご説明すると・・・
■ジョイント(継ぎ目)対策
・シーラー材ではなく、コテで塗る下地材で下地処理を行う
・仕上げ漆喰はフラット仕上げではなく、コテ跡を残すパターン(模様)仕上げを採用する
コテ塗りになるため、シーラー材より作業は多変ですが、下地材を塗ることでかなり対策になります。理由はコテで塗る分、下地処理の段階で厚みがつくため、パテ処理が多少雑な処理になっていたとしても、下地材塗りの段階でかなりフラットにできます。

また、漆喰の仕上げ方もパターン(模様)を採用することにより、最終仕上げに凹凸ができるので、下地処理で多少凹凸があってもわからなくなります。

もし、最終の漆喰塗りをフラット(平滑)で仕上げる場合は、下地処理にコテ塗り下地材をご利用することをお勧めいたします。