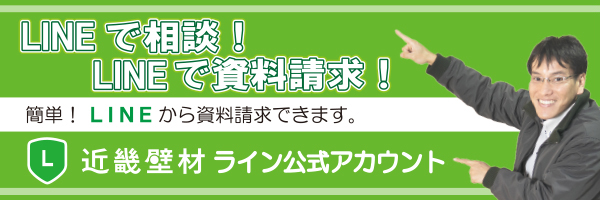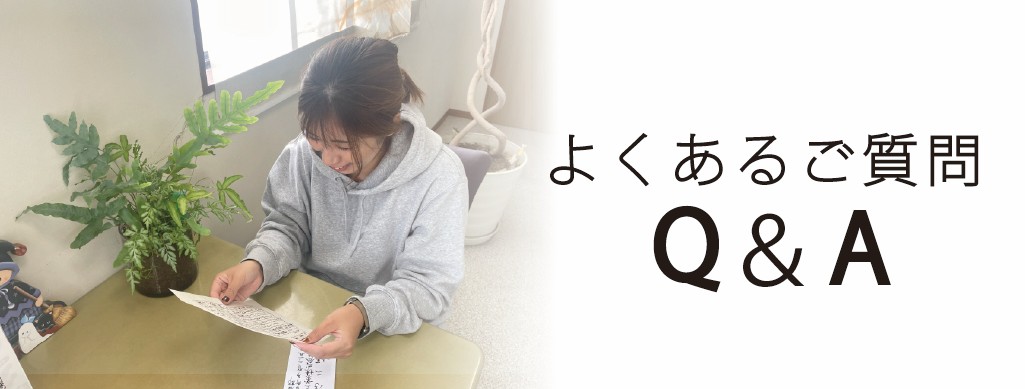白い漆喰は木と緑の植物との相性は抜群
当社の「漆喰(しっくい)」を購入していただいたお客様から施工後の完成写真が届きました。
施工したいただいた現場はリビングで、ビニールクロスの壁を塗り壁 漆喰にリフォームしていただきました。


天井の天然無垢材、緑の植物とのコラボでまるでカフェのようです。
木と漆喰、植物と自然由来のもので統一することで、落ち着きも感じる空間です。こんなところでゆっくりお茶を飲みたいですね。


これは写真を見た私の想像ですが、おそらく落ち着いた雰囲気を出すため、照明(ライト)の明るさ(明度)が少し落ち着いたものを採用しているように感じました。
建物の内部において壁は広い面積を占めるため、どのような素材やカラー、テクスチャ(デザイン)を採用するのかで空間のイメージを大きく変える事ができます。
空間のイメージやコンセンプトはあるがそれに合う壁を探している、壁に悩んでいる方はお気軽にお問わせください。
豊富な採用実績と、採用いただいた実物サンプルを元にご提案させていただきます。
ただいま、そのようなお客様のためにイベントを開催中です。
来社が無理な方にはオンライン対応もしております。興味がある方はご参加ください。